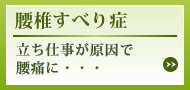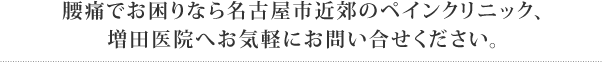用語集 は行 ま行
な行
は行
ま行
脳波(electoroencephalogram EEG)
ヒトや動物の脳において生じる電気のことで、一般に脳波を測定することを指して脳波をとるという。
内臓痛
胃・腸の収縮、伸腹展、けいれん、拡張などによって起きる痛みのこと。下痢などの際に腹部に感じる鈍い痛みが代表的。
針(鍼)治療(acupuncture)
主に中国の医学やその影響を受けた伝統医学(チベット医学やモンゴル医学)の理論に基づいて専用の鍼(針)を用いて皮膚・筋肉などを刺激することにより生理状態を変化させ、病気を治療する方法。
非ステロイド系抗炎症薬(nonsteroidal anti-inflammatory drug NSAIDS)
抗炎症作用・鎮痛作用・解熱作用を有する薬剤の総称のこと。字の通りステロイドではない抗炎症薬すべてを含む。
閉塞性動脈硬化症(arteriosclerosis obliterans ASO)
主に下肢の大血管に起こり、動脈硬化などの原因で慢性的に閉塞することによって、軽傷時は冷感、重症になると下肢の壊死にまで至ることがある病気のこと。
ペインクリニック(pain Clinic)
主として何らかの原因で痛みを呈する患者さまに痛みの治療を行う診療部門であり、神経ブロックによる治療を中心に行う医療機関である。基本的には麻酔科の医師が行う。
ヘルニア(hernia)
体内の臓器・組織などが、本来あるべき部位から脱出した状態のこと。
片(偏)頭痛(migraine)
女性に多い疾患で月に数回程度、頭の片側または両側が3〜70時間くらい痛む疾患のこと。原因は分かっていないが、三叉神経血管説やセロトニン説が言われている。なお「片頭痛(へんずつう)」は「偏頭痛」とも書いていた時期があるが、現在では片頭痛が正しい表記である。
片麻痺(hemiplegia)
片側にみられる上肢と下肢の運動麻痺。いわゆる半身不随の状態のこと。
迷走神経(vagal nerve)
第X脳神経のことで、頸部と胸部内臓、一部は部内臓に分布し、循環器系臓器や消化器系臓器の調節を担っている。
モルヒネ(morphine)
アヘンに含まれるアルカロイドで、チロシンから生合成される麻薬のひとつ。医療においては、癌性疼痛をはじめとした強い疼痛を緩和する目的で使用される。モルヒネは身体的、精神的依存性を持つが、WHO方式がん疼痛ラダーに従いモルヒネを使用した場合は、依存は起こらない。